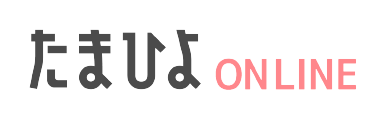泣き止まない、発達が遅いかも、かわいいと思えない…育児の悩み。ママパパが役割分担しない「かたまり育児」で解決!【小児科看護師papaPANDAインタビュー】

-
家事育児は「できるほうがやる」と決めたのに、結局ママばかりが負担しているという夫婦も多いのでは。そんな夫婦への処方箋「小児科看護師が寄り添うはじめてのかたまり育児」では、育児を「かたまり(2人)でやる」スタイルを提唱しています。そこで、同書の著者であり、小児科看護師で2児の父でもあるpapaPANDAさんにインタビュー。家事育児を「かたまり」で行う方法やメリットを、お悩み別に聞きました。
「かたまり育児」でしんどさを半分こしよう
――papaPANDAさんは、著書内で育児を「できるほうがやる」ではなく、「かたまり(2人)でやる」という「かたまり育児」を提唱しています。「かたまり育児」の具体的なシーンを教えてください。
papaPANDAさん(以下敬省略) たとえば、「赤ちゃんが泣きやまない」「なぜ泣いているのかわからない」というシーン。抱っこして、おむつを替えて、授乳して、それでも泣きやまないと、ママまたはパパはツラくなりますね。この過程を2人「かたまり」で行うのが「かたまり育児」です。
もし、ママが抱っこして困っているなら、パパは自分の頭の引き出しからアイテムを渡してあげてください。「抱っこを代わる」も、もちろんアイテムの1つですし「縦抱きより横抱きのほうが落ち着くかも」「昨日は、この揺らし方で泣きやんだよ」など、泣きやむための情報提供もアイテムです。そうしながら、しんどさを半分こするんです。また、「僕が抱っこを代わるから、向こうでコーヒーを飲んでおいで」といったいたわりのアイテムも持っていてほしいと思います。
――泣きやまないときは、ただ抱っこを交代するだけではなく、夫婦という「かたまり」で解決していくんですね。ほかにも、「かたまり」だからこそ解決できる例を教えてください。
papaPANDA 子どものかんしゃくも、いい例です。子どもは、かんしゃくを起こしたとき、自分で原因をうまく言葉にできないので、大人が「これが嫌だった?」「これがしたかったの?」と子どもの気持ちを代弁して選択肢を差し出しますが、なかなか当てられないと苦労します。このとき、ママパパが2人で選択肢を出していけば、選択肢は2倍。当たる確率が上がるわけです。夫婦で「かたまり」になって、子どもの気持ちをどんどん言語化してあげましょう。
同様に、「ほめ方がわからない」「遊び方がわからない」というお悩みにも、ママパパが「かたまり」で子どもと接することが有効です。それぞれ得意な方法で「遊ぶ」「ほめる」をするだけで、バリエーションは2倍になります。